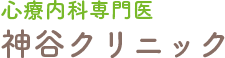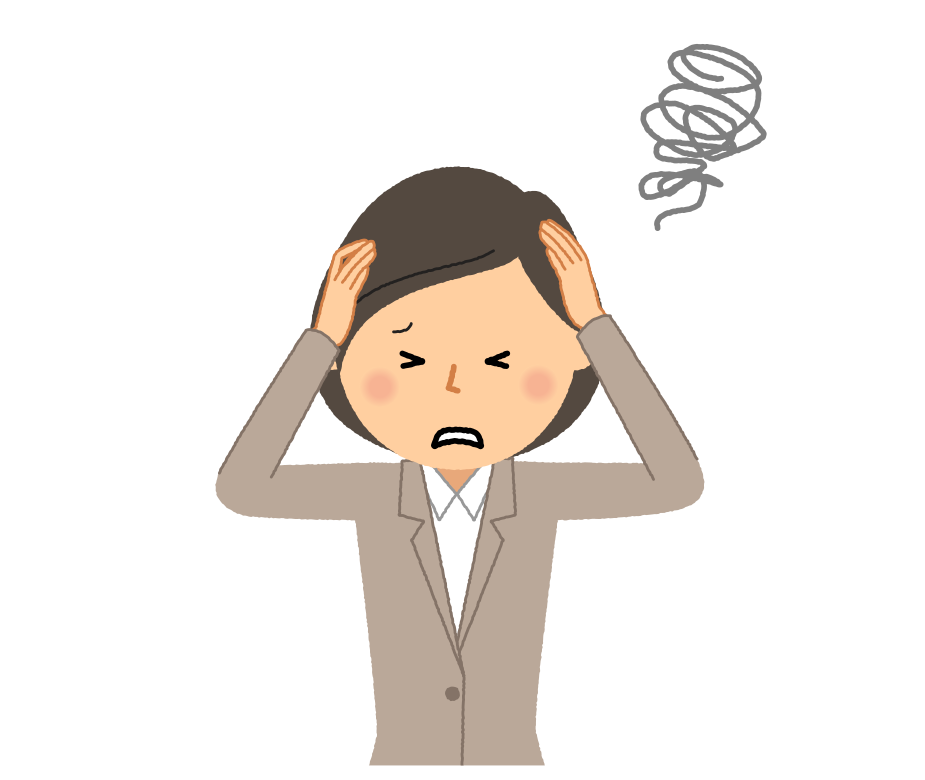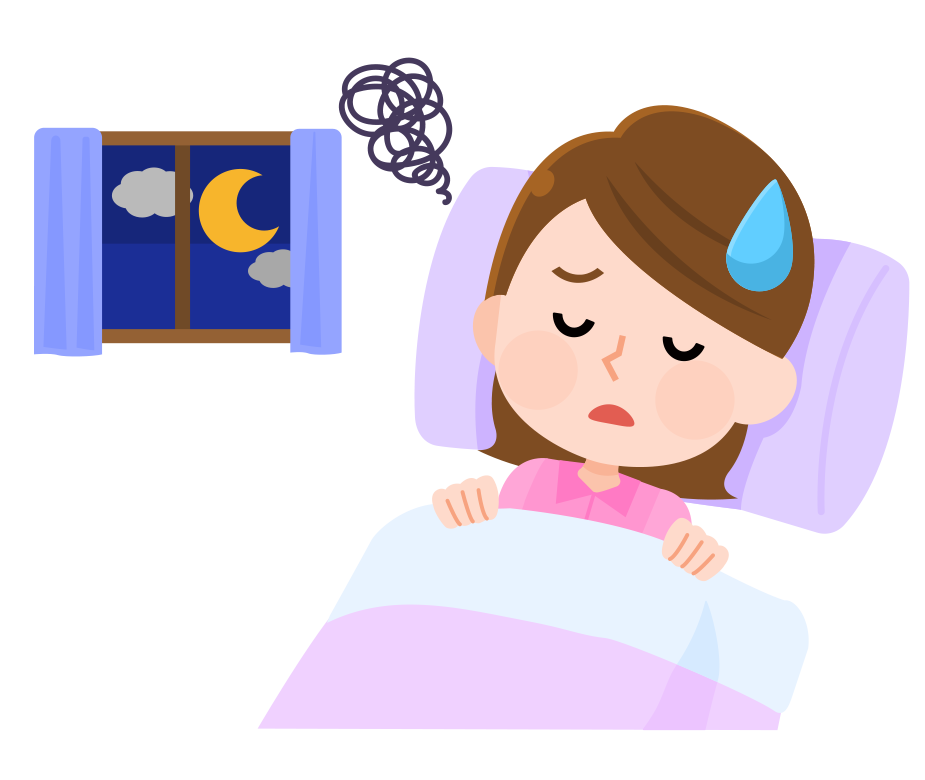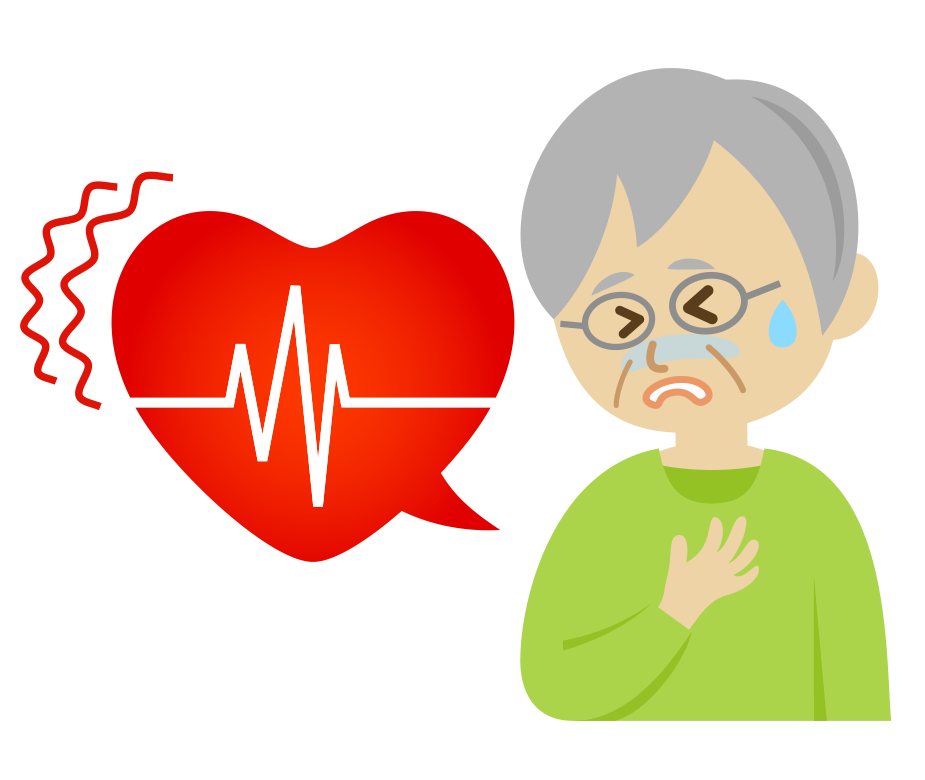診療案内
Treatment
このような症状のある方、ご相談ください
身体の不調
- 眠れない、寝つきが悪い、眠りが浅い
- 朝起きられない、昼間の眠気
- 疲れやすい・疲れがとれない
- 原因不明の頭痛・腹痛・身体の痛み
- 身体のムズムズ・そわそわ
感情や意欲の不調
- 落ち込む、気分が晴れない、悲しい、
- イライラする、怒りっぽい
- 何となく元気がでない、
- 集中が続かない
- 気持ちの高ぶり・テンションが高くなってしまう
対人関係の困りごと
- 他人とつきあうのが苦手
- 死別や別離がつらい
- 人前に出るのが苦手
- パートナー(配偶者・恋人)、親、子どもとうまくいかない
思考・行動の不調
- 考えがまとまらない、勉強・仕事が手につかない
- 緊張しやすい
- 乗り物に乗ることができない
- 誰かに見られている・狙われている気がする
- 声に考えや行動を邪魔される
その他
- 妊娠中・出産後の気持ちの不安定
- 育児・介護に疲れた
- とにかく不安
- 仕事に行けない
- 今通院しているが、お薬を減らしたい
- 障害年金、障害手帳、休職の診断書などの相談
うつ
うつ病は年々患者数が増加している病気で、誰にとっても身近な病気です。
心に現れる症状は、意欲・関心の低下、気分の落ち込み、イライラする、不安、焦燥感などあります。
身体に現れる症状としては、不眠・食欲低下、身体がだるい、めまい、頭が重いなどがあります。
早い段階で適切な治療を行えば改善する病気です。
治療は休養と安静、そして薬物療法です。
患者さんの状況に応じて、生活に関するアドバイス等を行います。
不安症・強迫性障害
・人と話すことができない
・人が多く居る場所に行けない
・電車やバスに乗れない
・学校のこと、家族のこと、友達のことが気になり仕方がない
・落ち着きがない、疲れ易い、集中できない、イライラする
・何度でも手を洗ってしまう
・何度も確認したにもかかわらず「家の鍵をかけたかどうか」が不安になる
睡眠障害・不眠症
睡眠は、人間にとってとても重要です。眠れないと、気持ちが晴れなかったり、ミスが多くなったりなど、様々な活動に悪い影響が出てきます。また近年では、不眠は生活習慣病を引き起こす一因であることもわかってきています。「忙しくて寝る時間がない」という方も多いことと思いますが、大事なのは「睡眠の質」です。また睡眠障害の原因はストレスなども関連しているといわれています。
認知症
こんな症状はありませんか
・新しいことが覚えれられない
・忘れっぽくなった
・今までできていたことができなくなった
・怒りっぽく攻撃的になった
・意味もなく徘徊する
・同じことを何度も言ったり聞いたりする
・関心や興味が失われた
・ものを盗られたと言う
認知症は根本的に治すための治療法はありませんが、お薬で進行を遅らせることはできます。
統合失調症
幻覚や妄想といった症状が代表です。また、意欲の減退や喜怒哀楽の感情表現が乏しくなります。
幻聴や被害妄想により、自分自身の思考や感情などがコントロール出来なくなり、学業、仕事、生活に支障を来たします。
思春期から青年期にかけて発病することが多いと言われていますが、この段階で受診せず中年期を過ぎてから病気が発覚することもあります。
長く付き合っていく病気と考えられます。
治療は、まず薬物療法を行います。
通常の生活が難しい患者さんには入院を検討することもあります。
パニック障害
混雑した乗り物や人混み、狭い室内にいることなどがきっかけとなり、突然の息苦しさ、動悸、発汗などの自律神経症状が発作的に出てくる病気です。
このような症状を繰り返すことで、通常何も症状が出ていない時にも「また発作が起こるのではないか」という不安感に苦しめられるようになります。この不安により次第に発作が起きやすい状況を避けるようになり、乗り物に乗れない、人混みに行けないなど日常生活が制限されるようになってしまいます。
治療は、まずは薬物療法で症状の軽減及び予防を行います。抗不安薬や抗うつ薬など、パニック障害に有効であることがわかっているお薬を使います。精神療法的なアプローチを組み合わせることもあります。